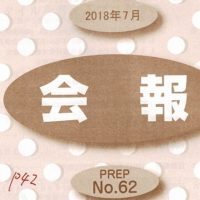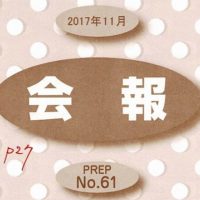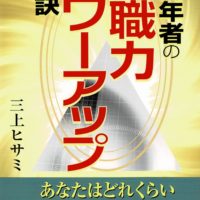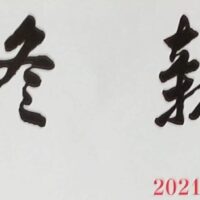- ホーム
- 高齢社会でいかに生きるか, 日記
- 再び高齢者問題を議論する
再び高齢者問題を議論する

酒田市の社会福祉士T氏の活動は認知症の高齢者が増加したことを踏まえ、
地域で「成年後見人制度」を充実させようということである。
将来的には元気な高齢者が成年後見人となって、
認知症の高齢者をサポートする、
いわば「老老」支援のような仕組みをつくることである。
ところで、一方の議論では認知症にならないためにはどうすればよいかである。
そこで筆者の実母の例を紹介したい。
母は本年9月20日で米寿の88歳を迎える。
青森県津軽の北部に生まれ地元に嫁いだ。
私たち4人の兄弟を育てた。
そして、家督の兄に嫁さんをもらった。
60歳過ぎに夫(筆者の父)を亡くした。
義姉は工場に勤務する。もちろん兄も会社勤務をしながら農業を行っていた。
母の大きな役割は孫の子守りと御飯炊きだった。
孫を相手にし、野菜を作り、近所の友人と語るのが日課のようだった。
ところが次第に状況の変化と共に認知症の兆候が現れた。
①孫が成長し、実家から独立した。
→役割がなくなった
②畑には腐った野菜など放置するようになり、
後かたづけに追われる義姉から畑づくりが禁止された。
→役割がなくなった、趣味活動が不可
③義姉は不況のあおりで工場勤めをやめ、実家で農作業を本格的に行うようになり、
母と接する時間が多くなった。
④母の友人が亡くなり、話し相手がいなくなった。
→本人曰く「寂しくなった」
⑤もちろん、母は高齢になり、同じことを繰り返す会話をするようになった。

以上のことから、認知症の症状が顕著になり、
①義姉から提言があったこと
②帰省した際に義姉から怒られている母の姿を見るに堪えない
ことから、入所させることにした。数年前のことでした。
一年に一回里帰りをして、施設を訪問して驚くことがある。
母の顔色がとても明るく元気なのである。
実家にいる頃には見たことがない。
恐らく役割があり、話す相手がいるからでしょうか?
あるいは恐い義姉の顔を見なくてもよいから?
(義姉に失礼ですが、本人の気持ちを察すると)
どうも入所させた頃は「姥捨て」ではないかと葛藤した。
最近は施設に入れて良かった気がする。
写真は2020.9.6挿入した。